1. イーサリアムとは?
イーサリアム(Ethereum、ETH)は、2015年に誕生したブロックチェーンプラットフォームであり、その基軸通貨が「ETH(イーサ)」です。単なる仮想通貨ではなく、プログラム(スマートコントラクト)をブロックチェーン上で実行できるのが最大の特徴です。
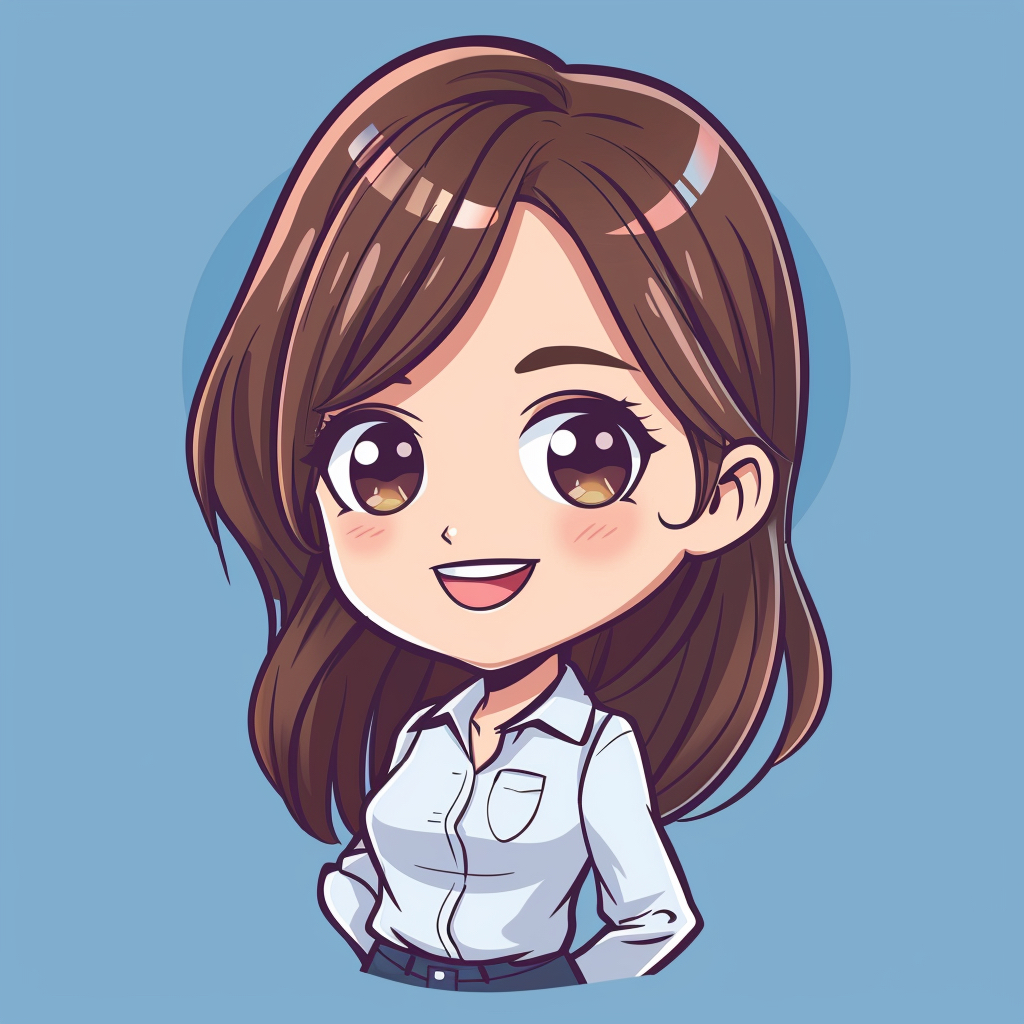
ビットコインとイーサリアムって、何が違うの?
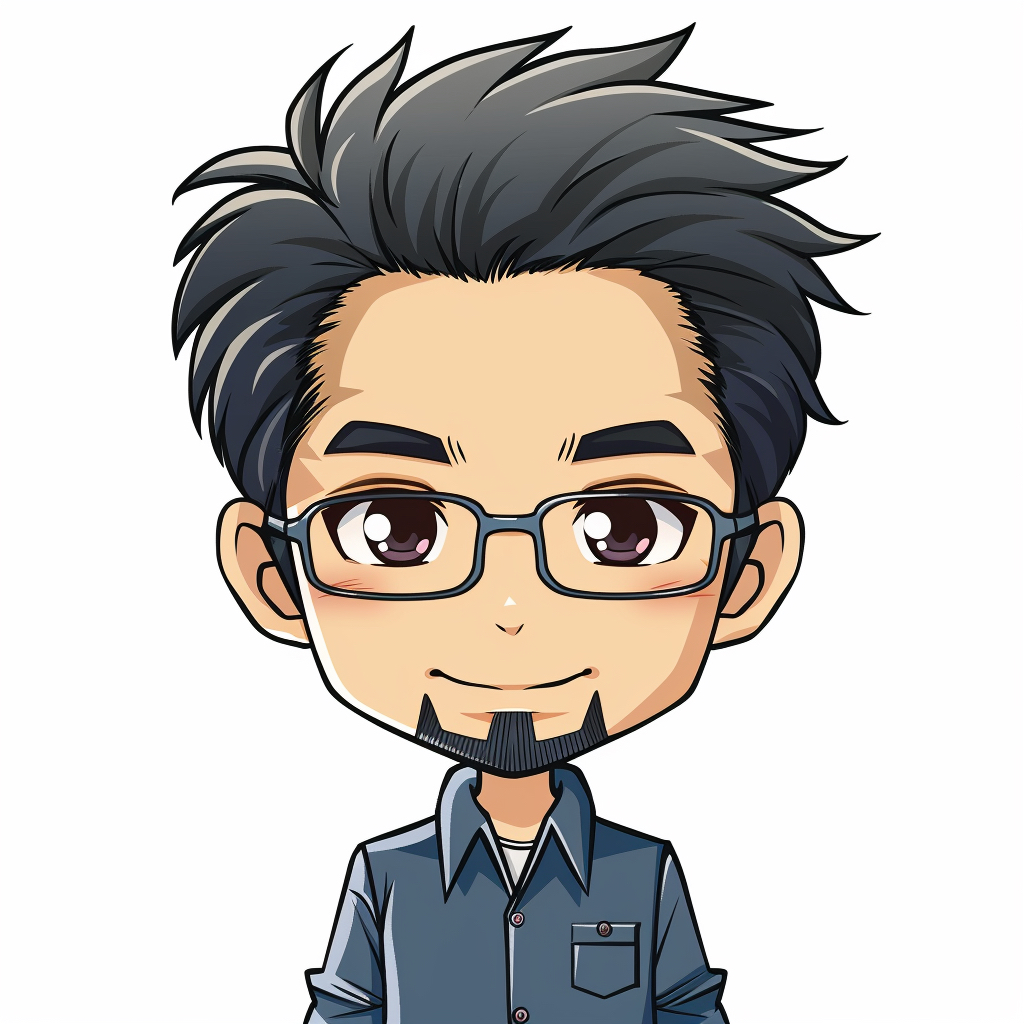
ビットコインは“価値保存のためのデジタルゴールド”。イーサリアムは“アプリやサービスを動かすためのプラットフォーム”だよ。

せやな。XRPが送金特化なら、イーサリアムはブロックチェーン界のOSやな。
2. イーサリアムの特徴
● スマートコントラクト:契約や処理を自動化できる
ブロックチェーン上で条件に応じて自動的に契約や取引を実行できる仕組み。仲介者が不要で、不正・改ざんが困難。NFTやDeFi、DAOなどWeb3の核を担います。
● 発行上限なし(ただし供給調整あり):EIP-1559で一部がバーンされる
ETHには上限がありませんが、2021年のEIP-1559により取引手数料の一部(ベースフィー)が自動焼却(バーン)。需要が高いほど実質供給が絞られ、デフレ的に振る舞う局面もあります。
● コンセンサス(PoS):2022年のマージでPoWから移行し、省エネ化
2022年9月のThe MergeでPoWからPoSへ。ETHをステークしたバリデーターが承認を担い、電力消費は大幅削減。環境面・機関投資の観点で追い風になりました。
● 拡張性:DeFi、NFT、DAOなど幅広く利用可能
通貨に留まらずdAppsの基盤として活用。DeFi(貸付/取引/運用)、NFT(所有証明)、DAO(分散型ガバナンス)、GameFi/メタバースなど多彩。手数料・速度の課題はレイヤー2(Polygon/Arbitrum/Optimism)が補完。
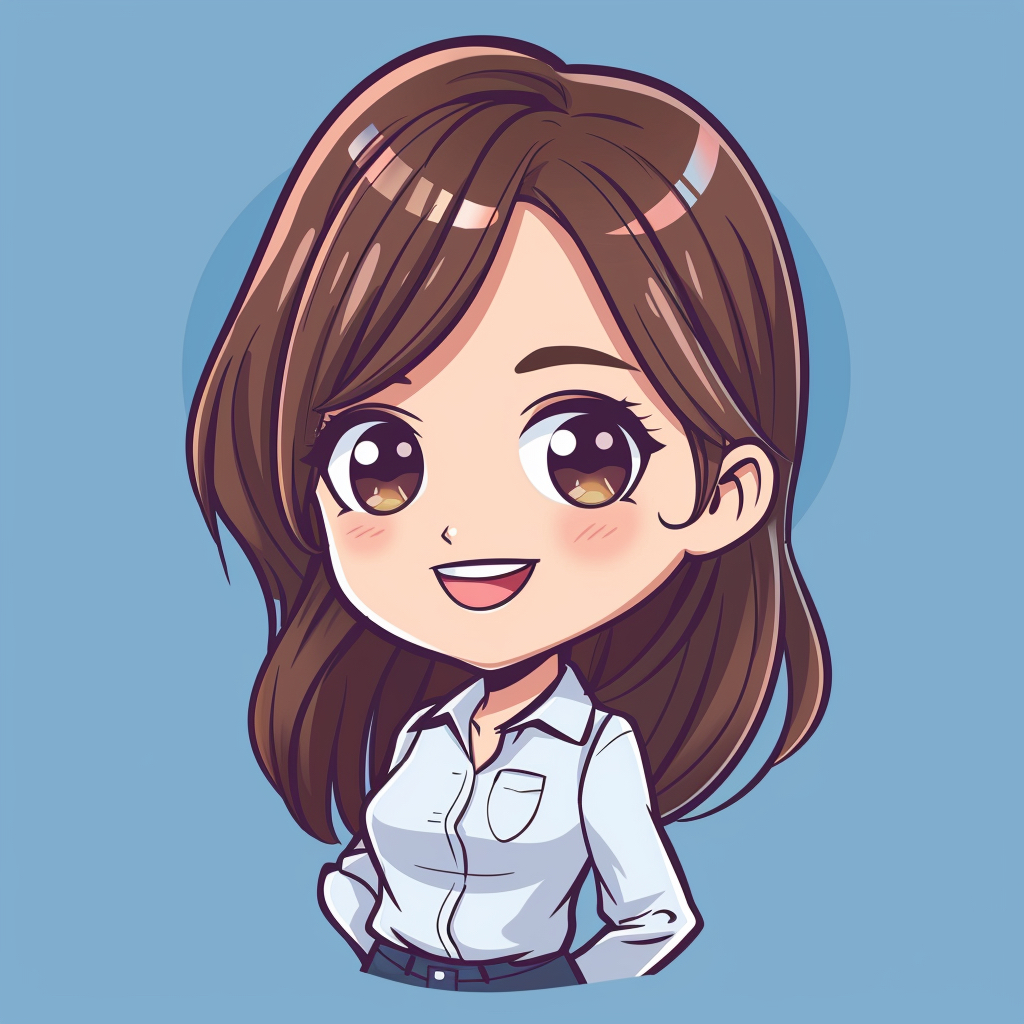
使い道がめちゃ多いね!
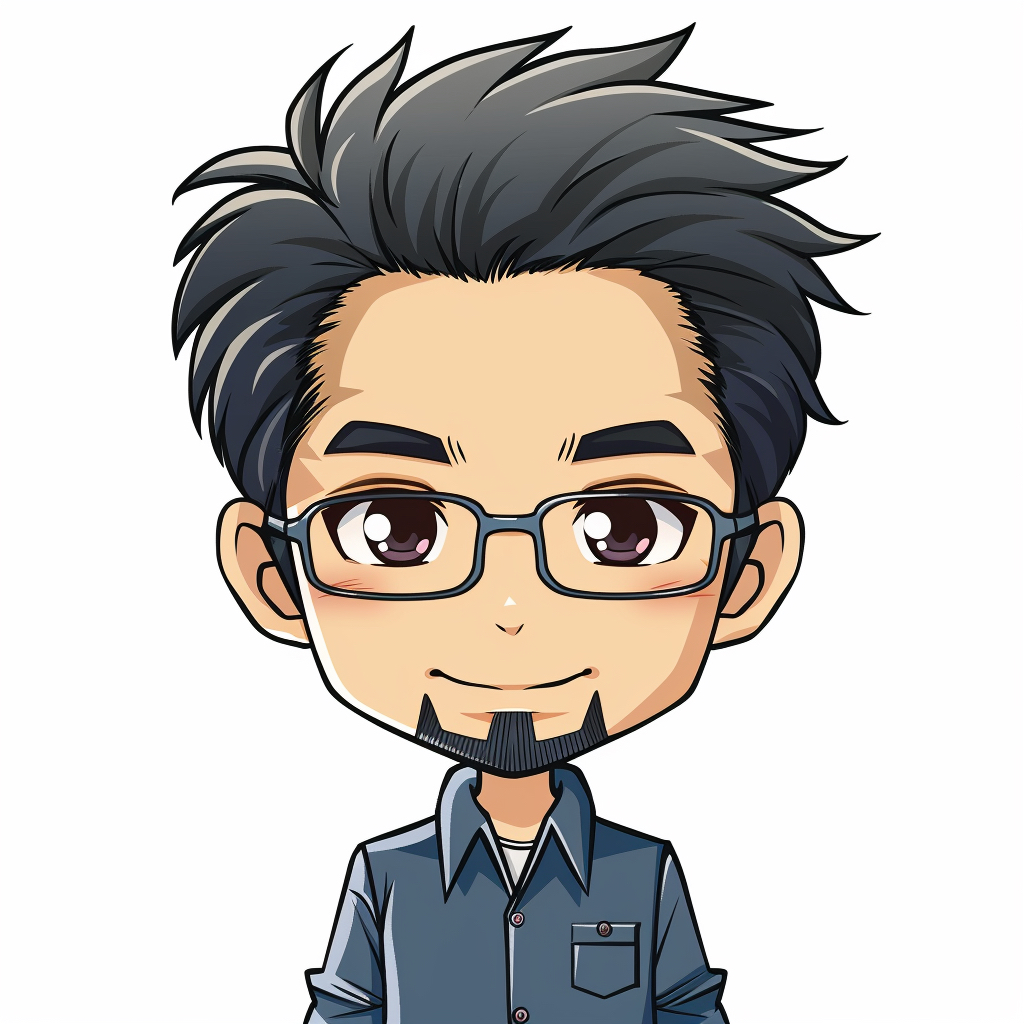
投資対象でありつつ、アプリや金融のインフラなんだ。

ガス代の高さは課題やけど、L2の発展で解決に近づいとるな。
3. イーサリアム価格変動の歴史(年表)
| 年 | 出来事 | 価格の動き |
|---|---|---|
| 2015年 | イーサリアム誕生 | 1ETH ≒ 数十円 |
| 2017年 | ICOブームで注目 | 約14万円 |
| 2018年 | 暴落(アルト冬の時代) | 約1万円 |
| 2020年 | DeFiブームで資金流入 | 約6万円 |
| 2021年 | NFTブームで最高値更新 | 約55万円 |
| 2022年 | マージ実行、PoSへ移行 | 約20万円前後 |
| 2024年 | L2拡大・ETF期待 | 約50万円超 |
4. イーサリアムの役割と目的
● 分散型アプリ(dApps)の基盤:金融、SNS、ゲームなど
中央サーバーに依存しない検閲耐性・透明性の高いアプリを提供。例:Uniswap(分散型取引所)、Lens Protocol(分散型SNS)、Axie Infinity/Sandbox(ブロックチェーンゲーム)。
● DeFi(分散型金融):銀行を介さない貸付・取引
スマートコントラクトで自動執行。Aave(貸付)、MakerDAO(DAI)、Curveなどで「新しい銀行体験」を実現。
● NFT(非代替性トークン):デジタル資産の唯一性を証明
アート/音楽/ゲームアイテム/メタバース土地の所有権をオンチェーンで証明。二次流通の収益分配もスマコンで自動化。
● DAO:トークン保有者の投票で運営される新しい組織形態
管理者不在でも提案&投票で意思決定。Uniswap DAO、MakerDAOなどが代表例。
ビットコインとの比較(役割の違い)
| 項目 | ビットコイン(BTC) | イーサリアム(ETH) |
|---|---|---|
| 誕生年 | 2009年 | 2015年 |
| 主な目的 | 価値保存(デジタルゴールド) | プラットフォーム(Web3のOS) |
| 機能 | 送金・価値保存 | スマートコントラクト、dApps実行 |
| 発行上限 | 2,100万枚で打ち止め | 上限なし(EIP-1559で供給調整) |
| 主な用途 | 長期投資、インフレ対策 | DeFi、NFT、DAO、RWAなど |
| 強み | 希少性・信頼性・シンプルさ | 実用性・拡張性・開発エコシステム |
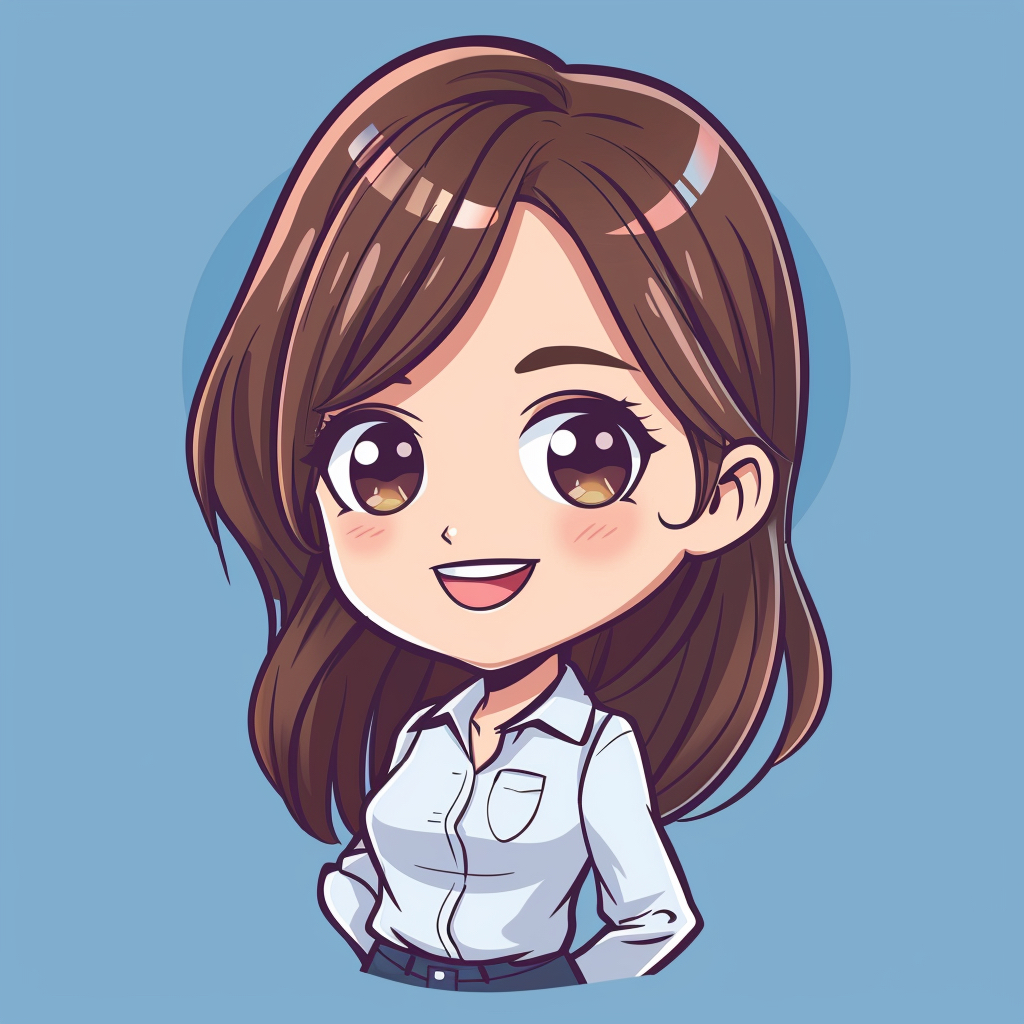
BTCは“守り”、ETHは“使う基盤”って感じだね。
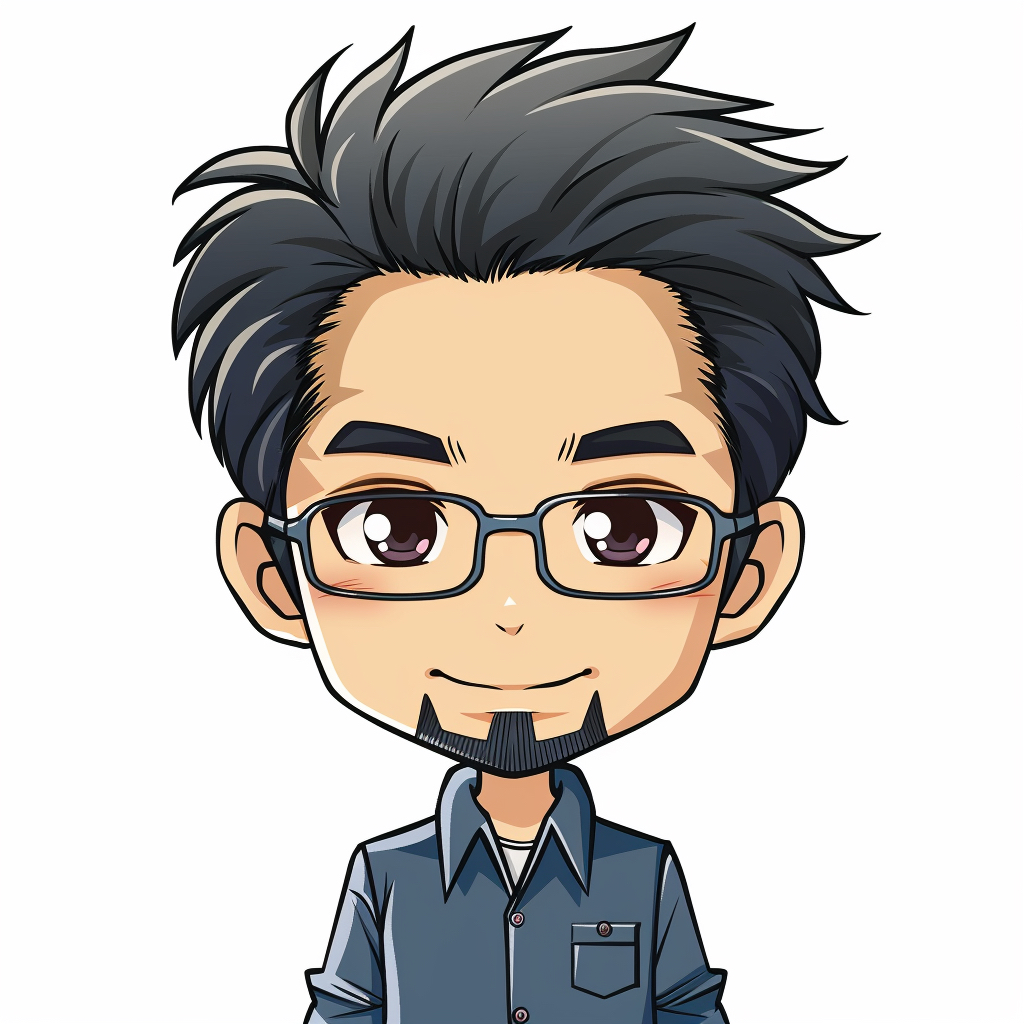
まさに。BTCは資産、ETHはインフラ。

ワイはXRP派やけど(笑)、この2つが双璧なのは確かや。
5. 世界での採用・注目ポイント
● 企業の参入:マイクロソフト、JPモルガンなどが実証実験
Azureでの開発支援、金融のQuorum活用、リワード×NFTなど、実務利用が進展中。実験から本番運用へ移行する企業が増え、信頼性が高まっています。
● NFT市場の中心:アート・音楽業界を変革
クリエイターが中間業者を介さずに収益化。音楽、チケット、ゲームアイテムまで拡大し、デジタル所有権の概念を普及させました。
● レイヤー2(L2)の台頭:PolygonやArbitrumでスケーラビリティ改善
混雑時の手数料高騰と遅延を、Polygon/Arbitrum/Optimismが低コスト・高速で補完。企業・ユーザー双方の参入障壁を下げています。
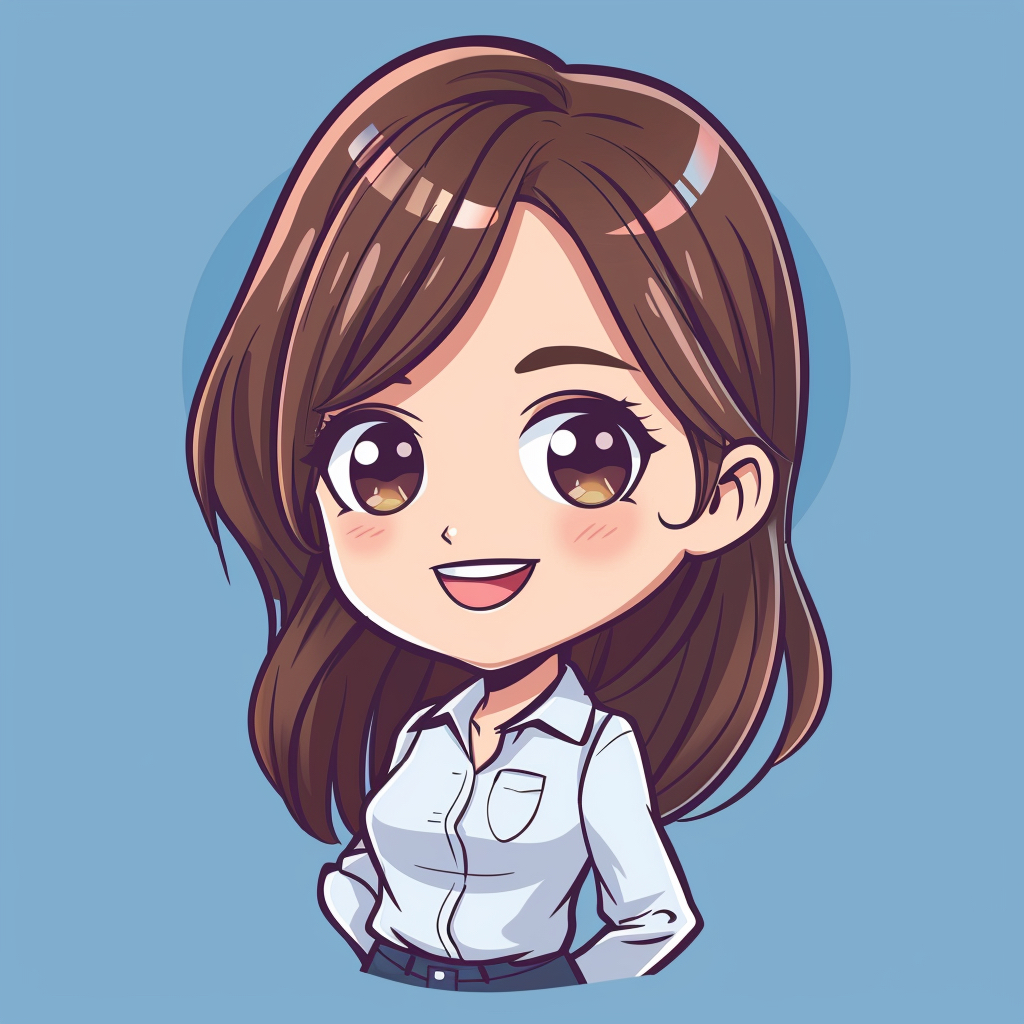
大企業も普通に使い始めてるんだ!
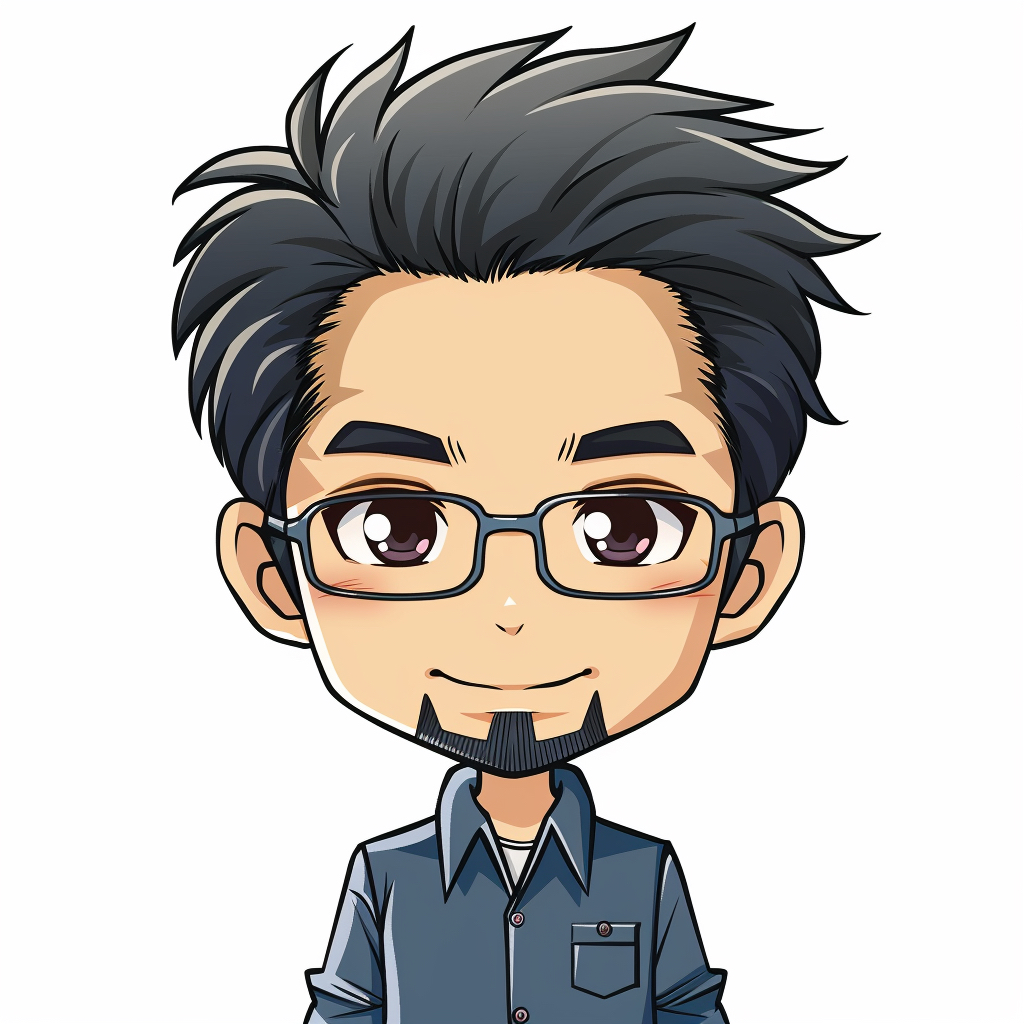
L2の発展と企業導入が、次の成長を引っ張るね。

実用はETHが強いわ。悔しいけど認める。
6. RWA(リアルワールドアセット)のトークン化
● RWAとは?
現実世界の資産(株式・債券・不動産・金など)をブロックチェーン上のトークンに変換し、権利移転や取引をスマコンで管理。小口化で一般投資家もアクセス可能に。
● イーサリアムが中心の理由
- スマートコントラクトで複雑な権利関係を自動化
- DeFiとの接続性が高く、担保化・運用が容易
- 透明性・検証可能性に優れ、トレーサビリティ確保
- 最大規模のエコシステムで企業導入の敷居が低い
● 具体事例
| 資産の種類 | 事例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 国債・社債 | 大手運用会社が米国債をトークン化 | 伝統金融がWeb3へ参入 |
| 不動産 | ビル/区分所有をNFT化して販売 | 少額での不動産投資が可能 |
| コモディティ(金など) | 金裏付けトークン(例:1トークン=1オンス) | 現物裏付けの安定性 |
| 美術品 | 高額アートの持分トークン化 | 分割所有で流動性向上 |
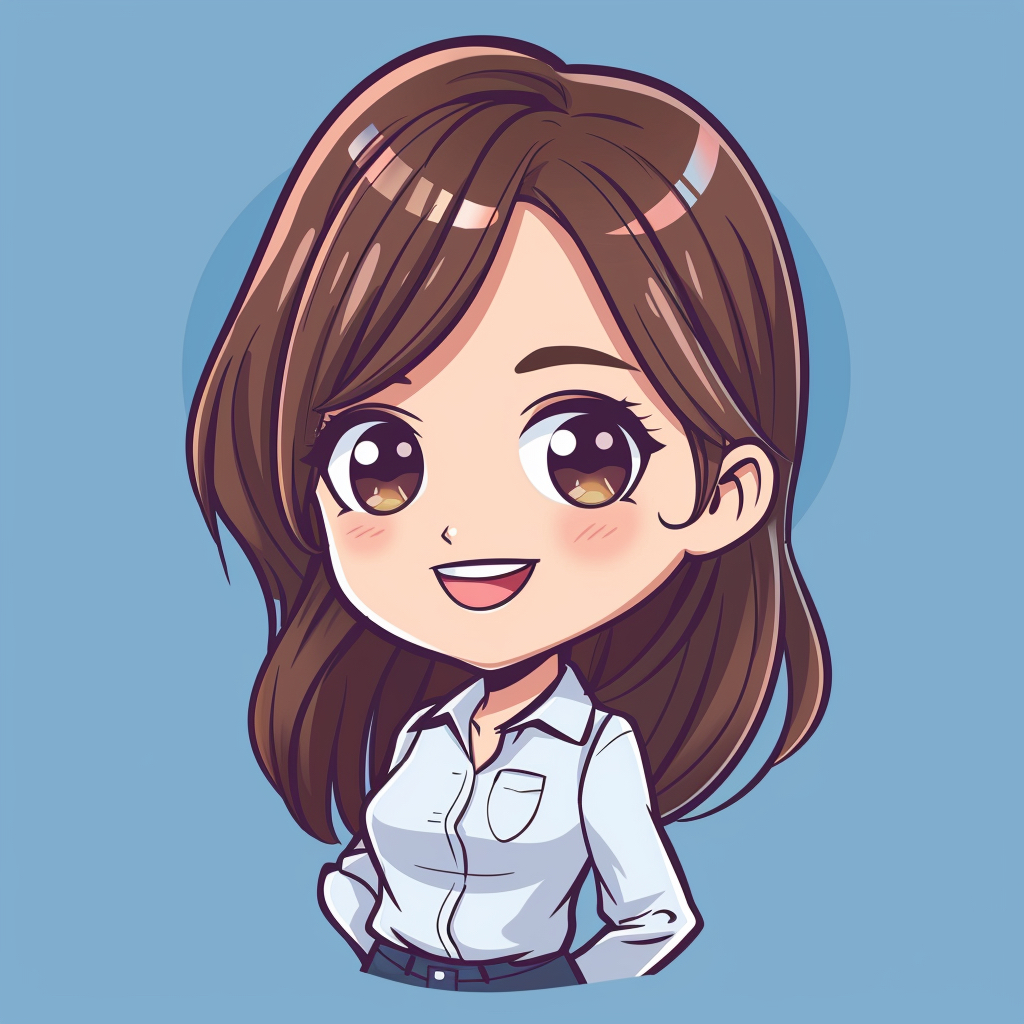
国債や不動産までオンチェーン化ってすごい!
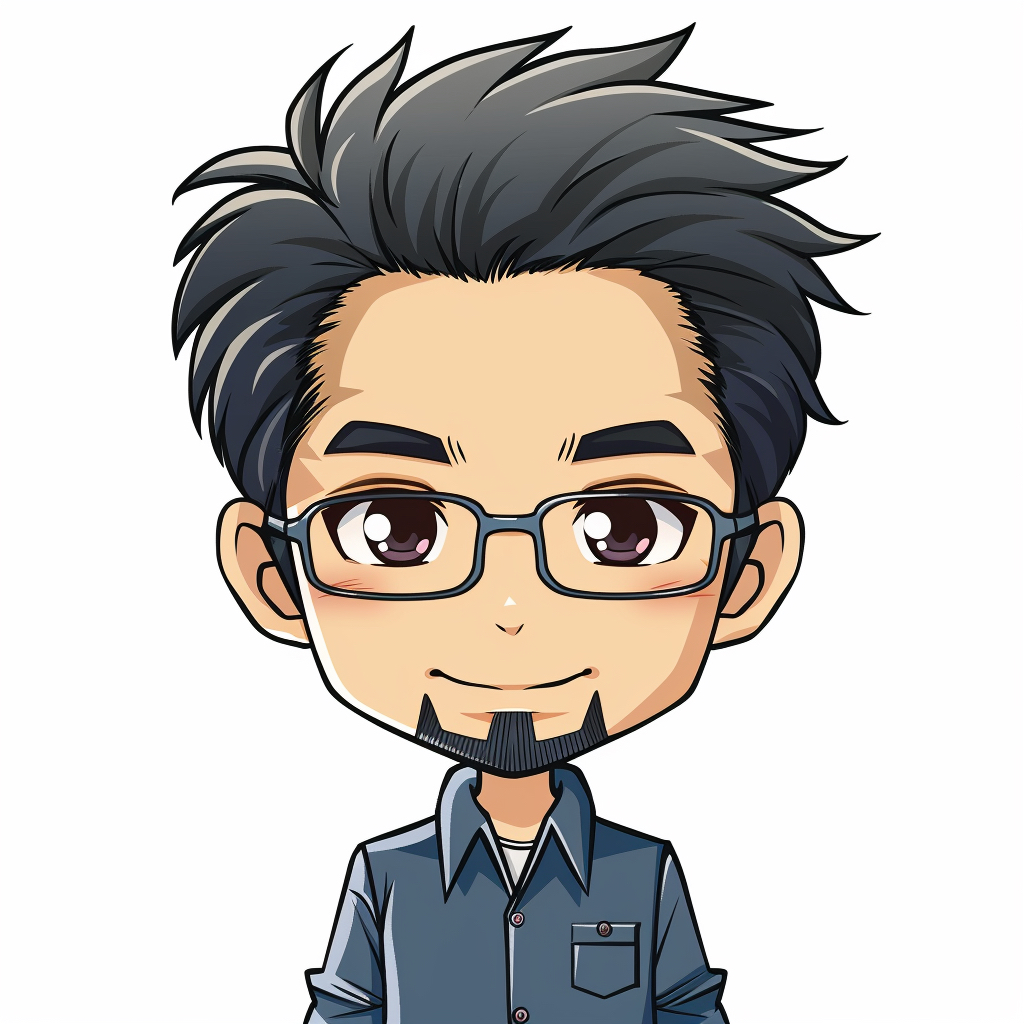
伝統金融とWeb3が融合し始めてる証拠だね。

これ広がったら、仮想通貨は投機やなく本物の金融インフラやな。
7. イーサリアム投資のリスクと注意点
● 価格変動の激しさ
短期で大きく振れるボラティリティ。投資は余剰資金で。
● ガス代(手数料)の高さ
混雑時は手数料が高騰。L2活用でコスト最適化を。
● 規制リスク
DeFi/NFT/RWAの規制動向次第で市場全体に影響。
● 技術的リスク(スマコンのバグ・ハッキング)
過去に大規模インシデントも。コード監査や運用体制の確認が重要。
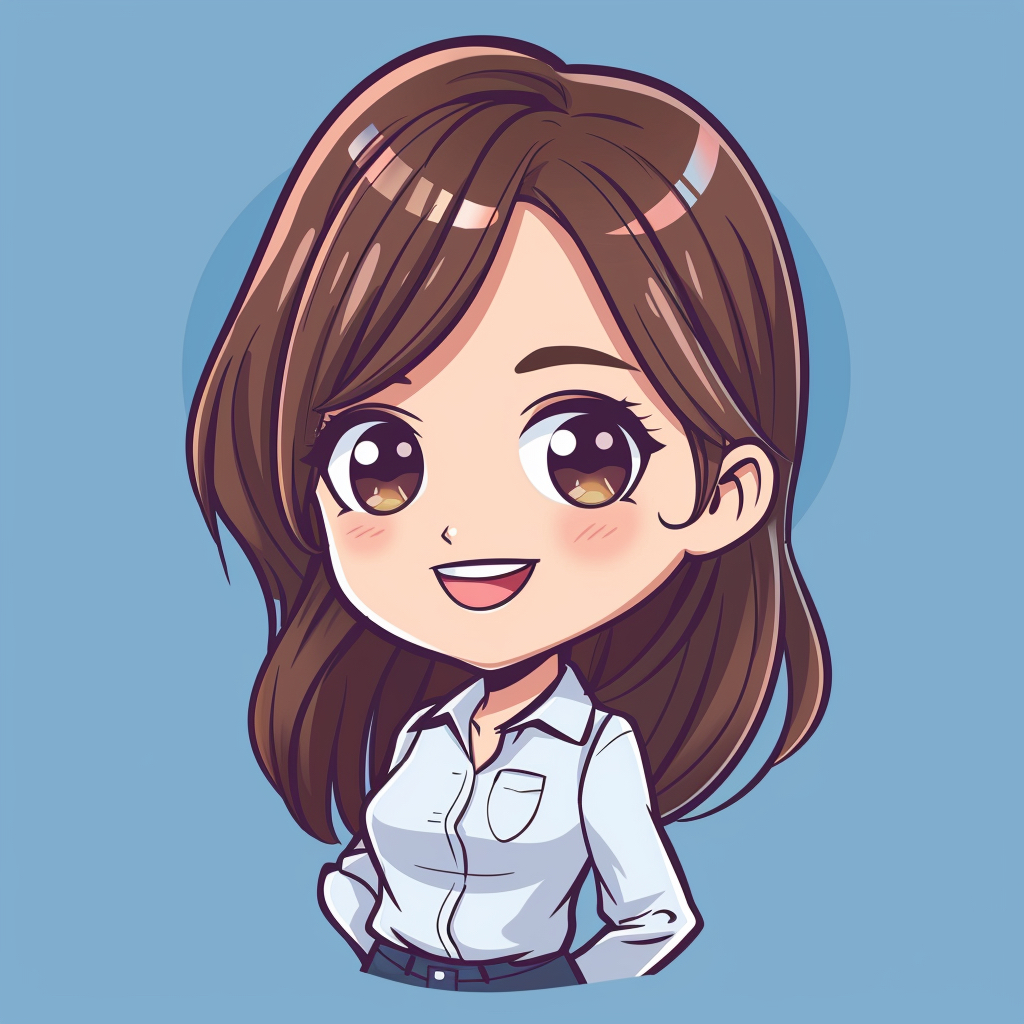
夢はあるけど、ちゃんとリスクも見ないとだね。
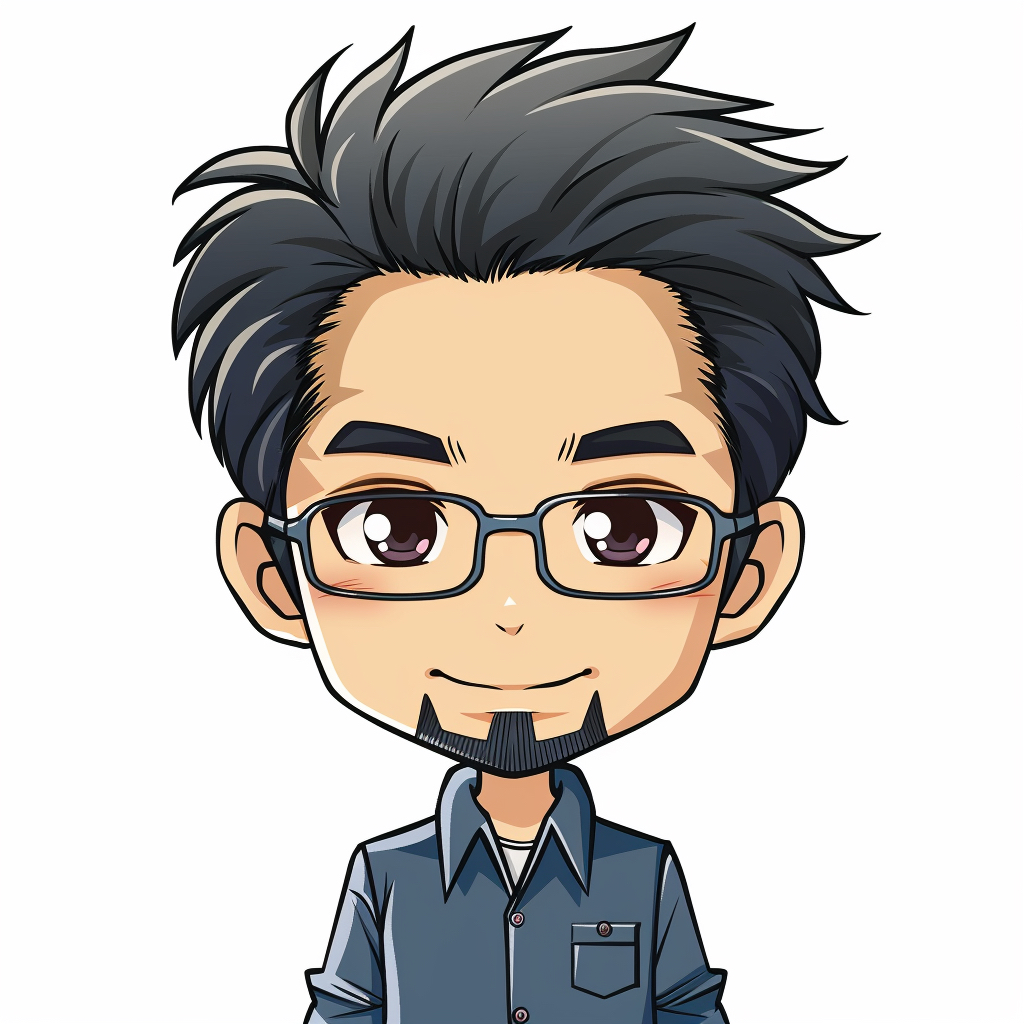
税制・規制・セキュリティを把握して使おう。

投資は自己責任。長期目線と分散が鉄則や。
8. まとめ
- イーサリアムはスマートコントラクト対応の基盤で、Web3の中核。
- DeFi・NFT・DAO・RWAまで用途が広く、実用性が強み。
- 発行上限はないが、EIP-1559のバーンで供給は調整。
- 価格変動は大きいが、L2やRWAなどの発展でエコシステムは拡大中。
- ガス代・規制・セキュリティのリスクを理解し、余剰資金での長期運用が基本。

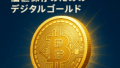

コメント